皆の衆!
こんばんはじゃ!
豊臣秀吉である!
此度の日記帳は『愛知の神社巡り』第13弾
『那古野神社』『名古屋東照宮』について紹介して参るぞ!!
いざ!!
『なごや』?『なごの』?2つの名がある神社
那古野神社は現世の名古屋城より南900めーとるに徳川殿を祀る名古屋東照宮と並んで建っておる。
この神社の創建は天王社から始り、延喜11年(911年)3月16日に醍醐天皇の勅命にて若宮八幡社と八王子社の隣に建てられたのじゃ。
天王社から始り、っちゅうことはこの神社の祭神は素戔嗚尊(須佐之男命)
前に紹介した津島神社の祭神と同じっちゅうことじゃな。


故にこの神社の神紋は『木瓜紋』
至る所に木瓜紋が飾られとる故に神社好きの者は来ただけでも何の神が祀られとるかは分かるわな。
さて、この神社。
『那古野』と書いて2つ呼び方がある神社でもある。
題名にも書いたわな。
『なごや』と『なごの』
徳川殿が『那古野』を『名古屋』と改名する前は最初の『那古野』を使っておった。
故に信長様が居城とされておった城は『那古野城』と書く。
じゃが、徳川殿がこの地に入ってきた際、多くの表記があっては民が混乱するっちゅうことで
『名古屋』に全て統一し、『那古野』は『なごの』と読ませるようになったとのこと。(徳川談)
っちゅうことで、
この神社の表記は『愛知縣神社名鑑』の中には『なごの』と振仮名が振ってあるのじゃが、
境内の名古屋市教育委員会が設置した説明板には『なごや』と振仮名がつけられおる。
実際はどちらでも間違いではないと言うことじゃろうなあ。
先ほど、この神社は延喜の時代に創建されたと話をした。
この時代は現世で申すと『平安時代中期』にあたる時代。
醍醐天皇の勅命にて創建されたと言ったが、
実はこの醍醐天皇は加賀前田家の先祖でもある菅原道真公を左遷させた人物。
そして菅原道真公は延喜3年(903年)に亡くなられおり、
その翌年から日の本各地で多くの飢饉や皇族関係者の不審死が続くわけじゃな。
醍醐天皇は自身が左遷させた菅原道真公の怨霊が悪さをしておると確信し、
その霊を鎮める為に日の本各地に多くの神社仏閣を建てられた。
この那古野神社もその1つでは無いかと、儂は推測しておるわけじゃ。
最初に書いたように、ここの祭神は牛頭天王。
即ち『素戔嗚尊』
天照大御神の弟神にあたり、強い力を持っておるわけじゃ。
じゃから、醍醐天皇は強い怨霊には強い神で対抗させようとしたのかもしれんわなあ。
那古野神社の隣にある『名古屋東照宮』
那古野神社の隣には徳川家康殿を祀っておる『名古屋東照宮』が建っておる。

この東照宮は元々、名古屋城の三の丸内にあった神社で徳川殿の九男で尾張藩初代藩主の徳川義直が
徳川家康殿の三回忌に合わせて勧請した神社でもある。
明治の折に名古屋鎮台が城内に置かれることになった際に、
この東照宮と那古野神社は城外に出されることとなり、尾張藩の藩校であった明倫堂の跡地に建てられることとなった。

じゃから今は徳川殿は築城者であるにも関わらず、城外に出されておると言うわけじゃな。
明治の折に神社が動かされた際に義直もこの神社に合祀され、
現在は父親である家康殿と共に祭神として祀られておる、っちゅうわけじゃ。
あくせす
名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線 『丸の内駅』1番出口から徒歩5分
※名古屋東照宮も同じ
ばっくなんばあ
尾張国三宮 熱田神宮
尾張国二宮 大縣神社
尾張国一宮 真清田神社
天王総本社 津島神社
清洲山王宮 日吉神社
末森城跡 城山八幡宮
名古屋総鎮守 若山八幡社
名古屋大須 三輪神社
名古屋大須 春日神社
名古屋桜通 桜天神社
名古屋高丘 冨士神社
尾張大国霊神社(国府宮神社)
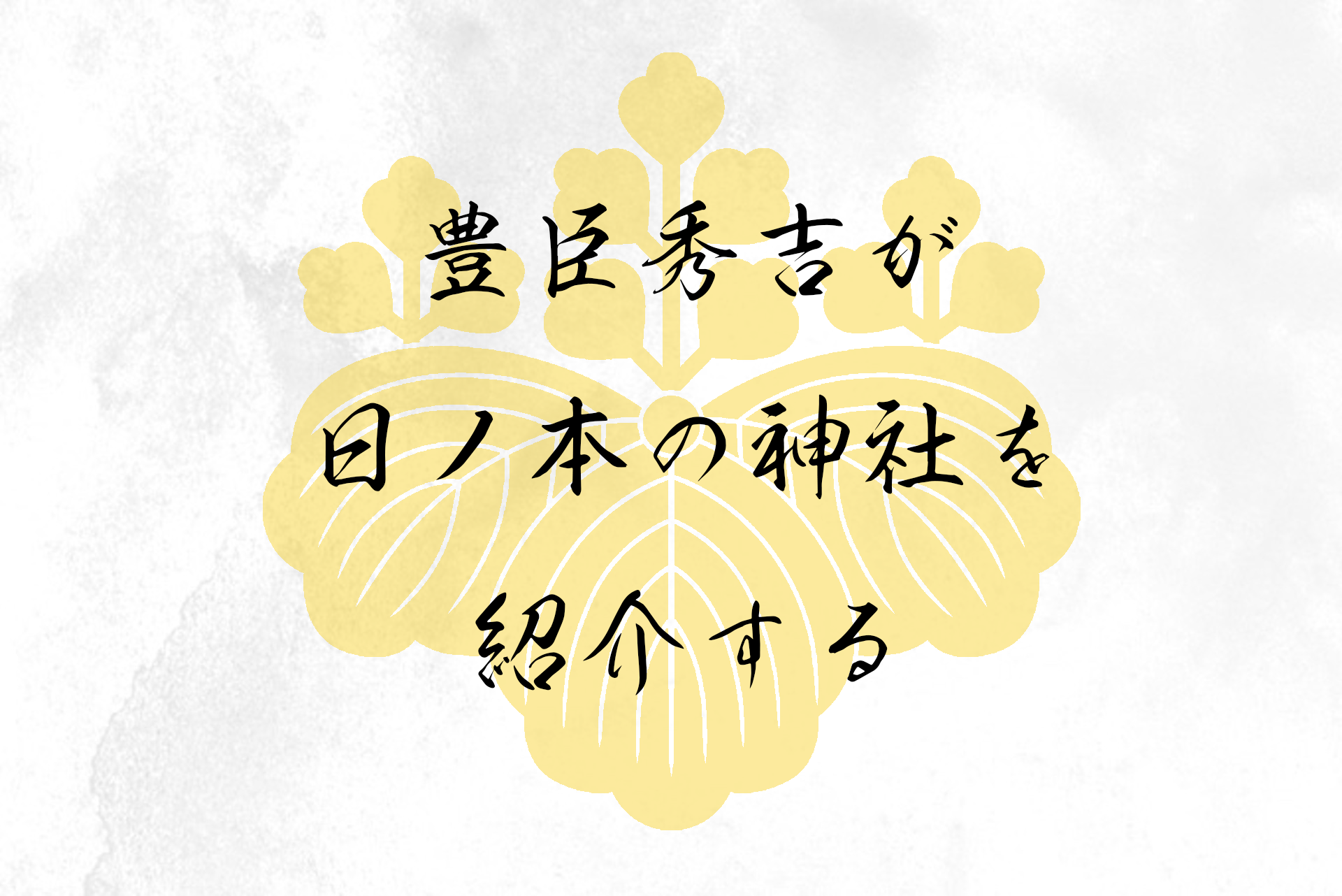


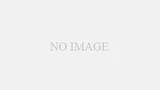
コメント