皆の衆!
こんばんはじゃ!
豊臣秀吉である!
此度の日記帳は『愛知の神社巡り』第14弾
『別小江神社』について紹介して参るぞ!!
いざ!!
電子網で流行り、若者に大人気の神社


別小江神社について、最初に言っておくことあるのじゃが。
実はこの神社はまだ詳しいことは分かっておらん神社なのじゃ。
別小江神社は現在ある場所より300メートルほど東北の千本杉というところにあり、
1584年に織田信長様の次男である織田信雄殿が命じて現在地に移されたこと。
そして江戸時代は六所明神と称していたこと、別小江神社と改称したのは明治初めのこと。
と言うように別小江神社には伝わっておる。
そう。
これだけなのじゃ。
また儂がこの日記帳にて良く出て来させておる「愛知縣神社名鑑」にはこう書かれておる。
「社伝に往古は六所明神と称したが、『本國神名帳』にある尾張國山田郡式内従三位別小江天神とある神社にして今の池を離る事壱町程東北の方千本杉と称する所に鎮座。
天正12年(1584)織田信雄の命に従い今の所に遷座し、修造料五百文を献進する。
明治5年、村社に列格、大正9年10月19日指定社となる。昭和20年空襲により焼失、昭和41年新構造により社殿を造営した」
実は今の別小江神社と現在の場所より300めーとる離れておった別小江神社は別の神社と思っておいた方がええのじゃ。
旧別小江神社については創建年も祭神も創建者も全て分かっておらん。
『延喜式』神名帳とやらには尾張国山田郡別小江神社と書かれておることから、
この延喜式神名帳が出来た時には既にこの神社が存在しておった。
じゃが、江戸時代に書かれた「尾張志」では「延喜式に見えて、今所在詳ならす」となっておることから、江戸時代には既に何もかも分からなくなったのであろう。
突然じゃが、この別小江神社は江戸時代には「六所社」や「六所明神」と呼ばれておった。
この名前で呼ばれておったのは信雄殿が移した新しい方の別小江神社。
実はこの辺り一帯には「六所神社」や「六所社」と名の付く神社や社が多い。
元々、この別小江神社も「六所社」と呼ばれていたが、明治の折に神仏分離令を行うに辺り、
色々と調査をした結果、ここだけは今の「別小江神社」と改名されたのじゃと、儂は思うておる。
じゃがこの神社について多くのことを調べると、
信雄殿の話が出てきたり、
我が家臣である浅野長政の義父でありおねの義父でもある浅野長勝様の話が出てきり、など、
この神社は本当に謎多き神社であることが分かるのじゃ。
そんな謎多き別小江神社。
祭神は伊弉諾命、伊弉冉尊、天照大御神、素戔嗚尊、月読命、蛭児命
となんと伊弉諾・伊奘冉家族が揃っておる。

そもそも先ほど話をした六所の名を冠しておる神社や社はこの6柱を祀っておることが多く、
意外と力の強い場所でもあったりするのじゃ。
もしかすると、この6柱を祀っておるから「六所」なのじゃろうなあ。
境内は多くの装飾あり。清正が持ってきた石も置かれておる場所
さてこの神社。
なぜ若者の間で話題になったかと言うと。
境内の装飾が見事なまでに「映え」を狙っておるかのように置かれておる。



またここの御朱印は多くの種類があり、これも若者に人気だそうじゃ。
そしてこの神社の境内には清正が名古屋城築城の際に持ってきたとされる石の残骸が置かれておる。

これは名古屋市は北区、味鋺にある味鋺神社近くに「清正橋」という小さな橋があって、
清正が名古屋城を築城する際に残った石を橋のようにして池に架けた、という伝説が残っておるんじゃな。
味鋺神社にはその「清正橋」を元あった場所から移設して、
境内に架け、保存をしておるそうなのじゃが。
実は意外にもこの地域ではそういった清正の伝承も残っておるくらいなのじゃ。
是非とも皆もゆるりと廻ると良いぞ。
あくせす
名古屋市営地下鉄・名鉄小牧線 上飯田駅1番出口から北西方向に徒歩20分弱
名古屋市営バス 名古屋駅から名駅13系統上飯田行き 金田町五丁目バス停下車、徒歩3分
ばっくなんばあ
尾張国三宮 熱田神宮
尾張国二宮 大縣神社
尾張国一宮 真清田神社
天王総本社 津島神社
清洲山王宮 日吉神社
末森城跡 城山八幡宮
名古屋総鎮守 若山八幡社
名古屋大須 三輪神社
名古屋大須 春日神社
名古屋桜通 桜天神社
名古屋高丘 冨士神社
尾張大国霊神社(国府宮神社)
那古野神社 名古屋東照宮
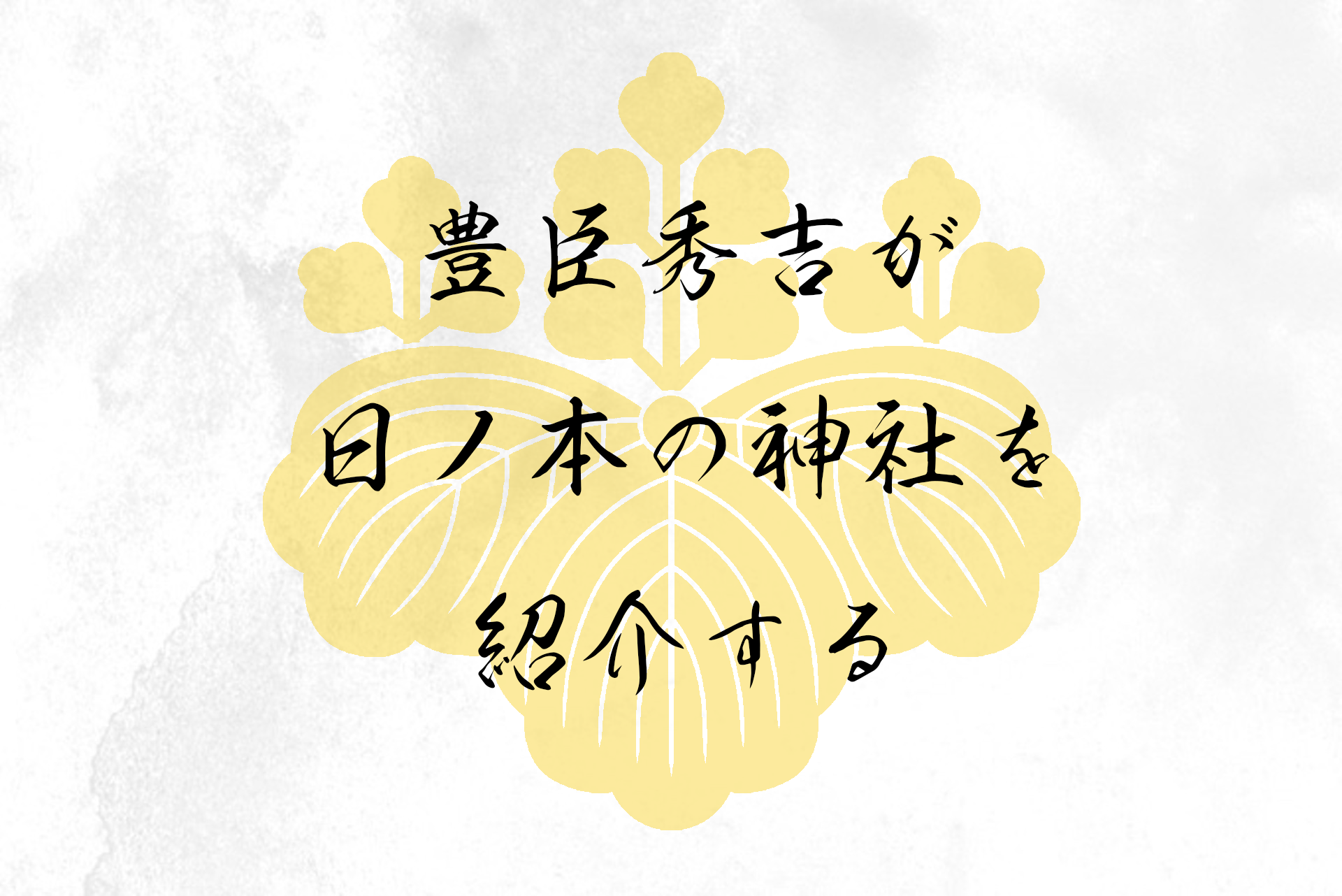

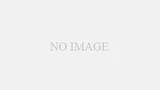
コメント