皆々、息災であるか
前田又左衛門利家である。
此度の日記帳は100名城の旅、三十九城目である。
此度紹介致すのは長きに渡り日ノ本の歴史の主軸を務めたかの家の根拠地である城じゃ。
いざ参らん。
足利氏館
此度紹介致すのは足利氏館。
見ての通り足利家の発祥の地である。
鎌倉時代後期から信長様が室町幕府を滅ぼすまでの約250年間は足利家の時代であった。
そして江戸幕府を開きし徳川家康殿も、
足利家(正しくは分流新田)を自称しておるから、誠に長き間足利家が日ノ本に影響を与え続けたと言っても過言ではない。
長きにわたって武家の棟梁となった足利氏発祥のこの地は国宝を持つ重要な中世の武家屋敷として残っておる。
早速武家社会の頂点足利家ゆかりの地を見ていこうではないか!
交通・行き方
JR上毛線『足利駅』歩いて十分、
東武伊勢崎線『足利市駅』からも同じく徒歩十分である。
東京駅からは新幹線を用いれば一時間半、
普通列車で二時間程度である。
因みに、東京方面から乗り換えで立ち寄ることとなる『小山駅』は、関ヶ原の戦いの折に東軍が上杉家への進軍をやめ関ヶ原に向かった小山評定が行われた場所。
徳川の天下にとって肝要なる場所である。
百名城スタンプの在り処
100名城の印判は、
敷地内にある鑁阿寺(ばんなじ)の本堂に置かれている。
参拝を終えたのちにいただくがよかろう。
足利氏館の歴史
足利氏はかの八幡太郎義家様の三男源義国様を祖とする河内源氏の一族である。
源頼朝様や義経様、義仲様は義家様の嫡男から続く一族である。
義国様の子である源義康様がこの足利の地を与えられたことから足利を名乗り始めたことが足利氏とこの足利氏館の始まりである。
鎌倉幕府の時代には将軍家一門の有力御家人として、国の政を支えたのじゃ。
この時に多くの分家を作っておって、
後に三管領となる、細川家・畠山家・斯波家、
四職の一色家、
三河を収めた吉良家や今川家など、
多くの家が室町や戦国時代に大きな勢力を持つ有力大名となっておる。
鎌倉時代を通して力を持っておった足利家であるが、

突如幕府から離反すると、
後醍醐天皇と共に鎌倉幕府を滅ぼし、
さらには後醍醐天皇からも離れて室町幕府を作り上げるのじゃ!!
足利家が京で幕府を開いたのちも氏寺として大切にされ、現世まで続いておる。
見所

方形の敷地とそれをぐるりと取り囲む水堀が我らを出迎えてくれる。
この形は武家の伝統的な作り。
源氏の有力な一族である足利家は格式高い伝統の武家屋敷を築いた次第であろう。
そしてその大きさも日ノ本屈指の大きさで足利家の威光を感じ取れるようになっておる。

そして一番の見どころと言えるのが、鑁阿寺の本堂である。
邸内に建てられた持仏堂が始まりであって、
1299年に築かれた本堂は改修を繰り返し現世にまで残っておる。
長い歴史を待つ貴重な建築として国宝に指定されておって、
足利氏の館とは知らずに足を運ぶ観光の者もおるようじゃ。
儂が訪れた折にも随分と賑わっておったぞ!
他にも重要文化財に指定されておる、

鐘楼や

経堂、
県の有形文化財となっておる

多宝塔や

東門、

西門、
そして館の入り口にあたる

太鼓橋と山門など、誠に多くの文化財が残っておる。
他にも市の指定文化財もいくつも残っておって、

現存する文化財の数は日ノ本有数と言えるのではないか!
今の日ノ本を作ったと言っても過言ではない名家の根拠地だけあって誠にまで手が行き届いた良き場所であったわ!!
蛇足
足利氏館はいかがであったか!!
現世のものが思う城とはちと様相が異なるやもしれん、
じゃが、これこそが武士の城である。
城に興味がないものも寺社の建築や趣が好きだというものもおろう、
そう言ったものにはかなりあつらえ向きである!
何よりも起伏がないでな、城は上り下りや登坂が億劫じゃというものにも勧めである。
戦国や武士といえば、
現世のものは戦国後期のことが頭に浮かぶけれども、日ノ本の歴史の根幹を築いた中世の武士について体感するのも良い経験となろう。
関東で城巡りを致すものには是非に訪れてほしい城であった。
是迄の城(ばっくなんばぁ
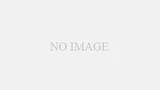

コメント
利家さま
こんばんは~
毎日毎晩厳しい暑さが続きますが体調はお変わりないですが?
聞くだけ野暮でしたね(^^ゞ
起伏がないという言葉にニヤリとしてしまいました~
多宝塔と聞いて荒子観音の多宝塔を思い浮かべました
写真からですがきっと大きい建物なんでしょうね
文化財が多くある足利氏館へ足を運んでみたいものです
日記の更新ありがとうございました
明日に備えてゆっくりとお休みください
利家様こんばんは!
日記帳の更新ありがとうございます(^_^)
足利氏館は、たしかに現世で考える「城」のイメージとは異なるかもしれませんが…
多くの文化財があり、城はもちろん寺社の建築や趣も好きな私にはとても興味深かったです!
写し絵も沢山ありがとうございます
時間をかけてじっくりと見てまわりたいなあ…と思いました(^_^)
次回の日記帳も楽しみにしています♪